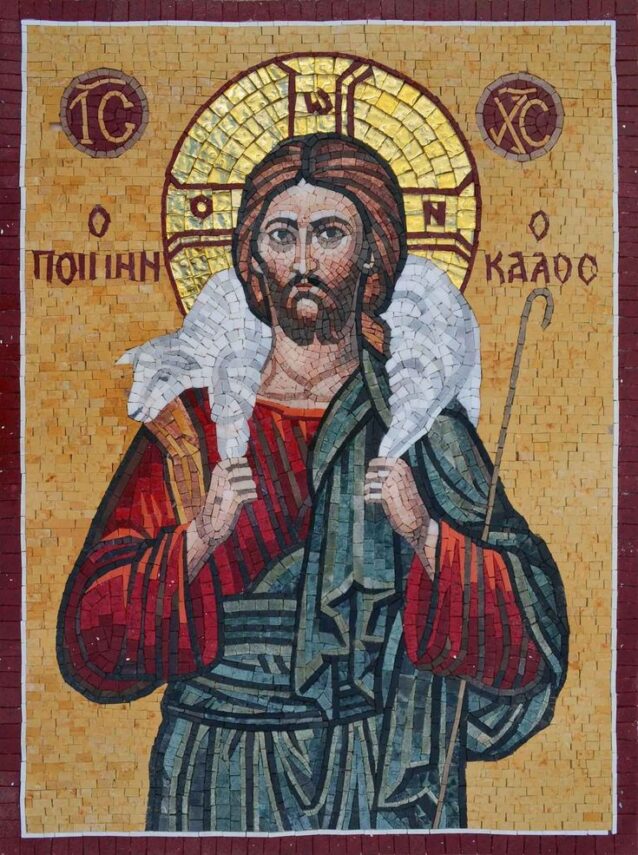マトフェイ4:12-17 2024/01/28 大阪教会
父と子と聖神の名によりて
預言者イサイヤはイイススがおいでになる七百年も前にこう預言しました。
「異邦人のガリラヤ、暗黒の中に住んでいる民は大いなる光を見、死の地、死の陰に住んでいる人々に光がのぼった」。
イイススはその預言通りに、生まれ育ったガリラヤ地方から「神の国は近づいた」と宣言しました。ご自身こそその「神の国」そのもの、「死の地、死の陰」の「暗黒」を、刺し貫く光、ハリストスであることを示しました。神に背いた私たち人が自ら招き寄せ、そこに閉じこもった死と暗黒のはざまに光、大いなる光がさし込みました。その光はそれまで暗黒に覆い隠されていた、私たちの生き方を、私たち自身に暴露します。私たちが罪にとどまりつづけるなら、すなわち、自分自身を自分の人生の究極の目的とする生き方、それによって失った神との交わりを、この世との交わりによって埋め合わせようという生き方に、とどまり続けるなら、その光はそんな生き方の不自然さ、惨めさ、そしてはかなさを私たちの目に露わにします。人はその光に正気では耐えられません。いや、露わにされた自分の姿に耐えられません。悪霊たちにとりつかれて崖から海になだれ落ちていった数千匹の豚と同じように、私たちも狂気の中で自滅してゆきます。神の国の到来にはが伴うこと、地獄に落ちるということの真の意味です。私たちをそこから救い出し導く神の愛であるハリストスを、ついに求めない者は、その光に背を向け自ら永遠の暗黒・地獄に留まり続けるでしょう。
しかしその地獄にさえ神の光はさし込みます。何ものも神の光を遮ることはできません。決定的な終わりの後にも、その光は「いや、決定的に終わったわけではないと」希望を差し出し続けるでしょう。シリアの聖イサアクが言うように、「地獄にいる人々も神の愛から切り離されていない」のです。
ニーチェという19世紀のドイツの思想家は、ハリストスを憎み「神は死んだ」と宣言しました。彼自身が狂気の内に滅び、彼の申し子たちは、すなわち神を信じることを屈辱とする人たちの魂は、いまも、ひきつけ、のたうっています。
「神の国が近づいた」からです。光を憎む者たちは光に敏感なのです。
光を憎む者たちにとって「この時」「今」は、この世界も、おのれの生命も一切が無へと転がり落ちてゆく「終り」でしかありません。しかし、光を愛する者らにはその「終わり」・終末は心躍る始まりです。神はもう私たち人間を威圧し、見下ろすお方ではありません。神は、そのようなお方であることを、自らなげうたれたのです。神は光としてすでに闇のうちにあります。神は人となりました。しかも「神の国が近づいた、悔い改めよ」と宣言されたのは、人々が商売や情事やはかりごとに明け暮れるカフェルナウムという街の喧騒のただ中でした。人の弱さのただ中で、人の弱さをよくご存じのお方が呼びかけています。光に走り寄るとは、神との交わりに方向転換するとは、このお方ハリストスに走り寄ることです。このお方を知り、このお方を愛し、このお方に従う、そしてこのお方が私たちのために十字架にささげ、私たちのために差し出されたご自身のいのちであるそのお体と血を分かち合う生活に躍り込むことです。分かち合う生活とは愛し合う生活です。この光の中では愛すること、愛のために自分を捨て苦難に耐えることは、もう道徳的な義務ではありません。天国へ入るための資格ですらありません。喜びそのもの、天国そのものなのです。
最後にアトスの聖シルワンのエピソードを紹介しましょう。 シルワン長老は神から引き離された地獄で苦しむ死者たちのために、たえず祈った。ある修道士が「無神論者たちは永遠の炎に焼かれるのです」と満足げに言った時、長老は当惑して言った。「天国に行ったあなたが、そこで見下ろすと、誰かが地獄の炎で焼かれている、それを見て幸せですか、愛は決してそれに耐えられません。すべての者のために祈らなければなりません」